 |
|
 |
|
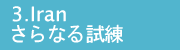 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
アジアへ (トルコ)
05
 今日は久しぶりの快晴だったので、風が心地よかった。船の上からは小高い丘が見える。そしてその頂上にはこの11日間毎日見てきたブルーモスクがそびえている。イスタンブールの中で一番好きな建造物が、このブルーモスクだった。正式名称はスルタンアフメット・ジャミイ。内側の壁や柱が青いタイルで飾られていることから、ブルーモスクと呼ばれ、外壁は青ではなく灰色と白を混ぜたような色である。けれども、青くないはずのブルーモスクは、ぼくが見るたびに空の色と重なって青く見えるのだ。そのたびにぼくは、名前のとおりなんて美しく青いモスクなんだと、ぽかーんと口を開けながら感激するのだった。
今日は久しぶりの快晴だったので、風が心地よかった。船の上からは小高い丘が見える。そしてその頂上にはこの11日間毎日見てきたブルーモスクがそびえている。イスタンブールの中で一番好きな建造物が、このブルーモスクだった。正式名称はスルタンアフメット・ジャミイ。内側の壁や柱が青いタイルで飾られていることから、ブルーモスクと呼ばれ、外壁は青ではなく灰色と白を混ぜたような色である。けれども、青くないはずのブルーモスクは、ぼくが見るたびに空の色と重なって青く見えるのだ。そのたびにぼくは、名前のとおりなんて美しく青いモスクなんだと、ぽかーんと口を開けながら感激するのだった。
遠くの海から眺めるブルーモスクは、今日はいっそう青く美しく見える。しかしそれももう見納めだ。
今ぼくはヨーロッパとアジアを隔てるボスポラス海峡を船で渡っている。これを渡りきれば正真正銘のアジアである。これからもまた独りで、しかも今度はもっと人の少ない過疎地を走らなければならない。治安も心配だが、それよりもこの後に控えている山道の方が不安要素が多い。
イスタンブールで地図を買ってそれを眺めた。ぼくがどんなルートを取ろうか決めあぐねるほど、トルコ東部は山岳地帯だった。アンカラが標高800メートルというのは日本にいるときから知っていたが、それより東では、もっと標高の高い町があることをその時まで知る由もなかった。ヨーロッパ製のその高級な地図には親切にも主な町の標高まで記載されていた。それによれば、ぼくが最短ルートでトルコの中心を突っ切る幹線道路を走ることにすると、地図上での一番標高が高い町は1857メートルで、最も高い峠は2300メートルである。1500メートル以上の町なんてそれこそ数え切れないほどある。
黒海沿岸の道を通ることも考えたが、この季節は毎日のように雨が降るというので、ぼくは散々迷ったあげく、雨よりは山を選択することにし、中央突破のルートで行くことを決めた。
船は15分ほどで海峡を渡りきり、船を下りると、そこはイスタンブール側と比べて、とても静かなところだった。イスタンブールの西側では、30キロも前から町が始まっていたのに、海峡を隔てたこの東の陸地では、少し走るとすぐに田舎の景色になった。東側にはまだ海が見える。
久しぶりということもあってか、自転車をこぐという行為そのものが、純粋に楽しい。よしよし、おまえも宿の奥底に閉じこめられて窮屈だっただろう。もう思う存分走っていいからな。
「さあ、いっくぞー」
すでにアップダウンが激しい、ゼーゼーぜ〜。そして車が猛烈に危ない、ヒヤヒヤヒヤ。ヨーロッパのクラクションは「車が来てるよ」とやさしい感じだったが、ここでのクラクションは明らかに「どけっー」という感じだ。「あぶねーよ」と叫びたいけど、ここは車最優先の国なのだ。
目的地のイズミットに早く着いたので、次の町まで行けると思っていつものように無茶をした。日が暮れるのが6時半と早く、アダパザルと呼ばれる街に着いたころには辺りは真っ暗だった。ぼくは自転車のライトすら持っていなくて、この場所が町のどこに位置するかも全くわからない。辺りは工場だらけで、とりえずここは町のはずれだということ、そしてきっとここの治安は良くないということだけは、本能的に確信した。そう思うと急に心細くなってきた。
「Otel?Otel?(ホテルはどこ?)」
と周りの人に聞き、とりあえず指を指されたほうに行ってみる。しかし行けども行けども真っ暗である。不安になりながら30分も暗闇を漕ぐと、やっと街中らしくなってきた。そこでまた一人の青年にホテルはどこだと聞くと、親切にも案内してくれることになった。
しかし案内されたところは、ベルボーイがいるような高級ホテルだった。一応値段を聞くと2000円だという。「安い」と思ったけれどヨーロッパならまだしも、トルコでホテルにこの値段は出せないので、もっと安い宿を探すことにした。
再び青年と一緒に歩き始めると、一人の中年男性が近寄ってきた。彼はその青年となにやらトルコ語で話しこみ、その話が終わると、青年はぼくに身振り手振りで話し掛け、急に去っていってしまった。わけがわからずポカンとしているぼくに、その中年男性はついてこいと指図した。とりあえず不安ながらも彼の後ろをついていく。町中にいる誰もがぼくを見つめていて、誰もが興味津々の顔をしていた。この町にはきっと観光客など来ないのだろうな。
連れていかれた先は先程よりもいくらか安そうなホテルだった。値段は600円、地方にしては高いと思ったが、部屋に入ってみると、シャワーもトイレも付いていたので申し分のない値段だと思った。
夕食を食べようと外に出ると、入り口には、先ほど案内してくれたおじさんが立っていて、ぼくを待っていたようだった。ぼくは疑いのまなざしで彼を見た。彼は実はホテルの客引きで、手数料でも請求されるのかと思ったが、話してみるとそれは大きな間違いで、ただの自転車好きの人の良いトルコ人だった。
彼は町を案内してくれて、食事までおごってくれた。珍しがってぼくにたかってきた子供の物乞いにもお金をあげていた。このおじさんといい、先程の青年といい、トルコ人はなんて親切なんだろう。イスタンブールのあの悪質絨毯売りと同じ人種とは思えないほどだ。
久々に自転車で走ったのと、150キロという距離と緊張感のせいで、宿に帰ると急激に疲れが襲ってきて、着替えもしないまま深い眠りの世界へと落ちていった。
後ろからの風に押されながら、気分良く田園地帯を走る。しかし今日の後半には難関が控えているので今の内に飛ばしておかねばなるまい。遠くの空が怪しい色をしているので一雨くるのかと不安になったけれど、昨日のおじさんの言葉を思い出し、その心配はないと思いなおした。
「今は自転車に良い季節だ、No wind . No rainだよ」
たどたどしい英語で彼はこう言っていた。しかし追い風だけど風はあるじゃないか。決して無風というわけではないので、彼の言ったことに少々不安になった。
3時過ぎ、問題の上り坂に着く。ここから一気に900メートルも登らなければならない。そんな高さはぼくには未経験のことだった。自転車で登る900メートルってどんなものなのだろう。このルートは昨日の、アダパサルおじさんお薦めルートだった。「坂は少ない」と彼は言った。しかし、900メートルを短い距離で登る、この坂の急なこと急なこと。
地図を見ると12%と書かれているところもある。12% というのは100メートル進んだ時に12メートルの標高を上っているということである。
実際登り始めると、それは想像した以上につらいものだった。ひたすら地道にこぐ、時速は5キロから6キロ。こぐのに疲れたら、自転車を押したが、押して登るのも大変なくらい急な坂だ。おーい 親父ー、これが坂が少ない道路かー!「ブオーン、ブブブーン」大型車があおりながら真横を通過する。へとへとになりやっとのことで坂を登りきると、辺りはすでに薄暗く、今日中に目的地に 着くのは不可能だと思ったので野営場所を探すことにする。
少し走ると、右手の林の奥に空き地らしき場所が見える。そこにテントを張ろうかと行ってみると、その開けた土地には、伐採されてから間もないような材木がたくさん積み重ねてあった。トラックが1台止まっていて、その近くには大きなテントが3つほど建っている。きこりの棲家とでもいうとこだろか。煙突からは煙が出ているので、どうやら誰か居るらしい。
今日はもう暗すぎて、これ以上走ることは不可能なので、この場所にテントを張ってよいかと聞くことにした。
「すみませーん」
そう叫ぶと中からはおとなしそうな若い女性が出てきた。当然のことだが、ぼくを不思議な目で眺めている。彼女は栗色の髪の毛を後ろで束ね、顔の色は白人のようだが彫りが深い。ああ、トルコ人は美人だなー。それはさておきテントテント。
「あそこにテントを張っていいですか」
英語で尋ねてみたものの、彼女は微笑みながら首をかしげる。
言葉がまったく通じないのだ。次に大きな動作で、ジェスチャーをしてみた。場所を指差し、空中に大きな四角形を手で描き、眠るしぐさをした。彼女は再び首をかしげる。どうやら通じていないようなので、実際にそこまで来てもらい、今度は地面に四角を描き、同じしぐさをしてみた。
「あーあー、いいわよ」
今度は縦に首を振っているので、勝手にそう言ったものと解釈し、テントを張ることにする。彼女は自分のテントほうに帰ると、隣のテントから15歳くらいの若者と、小さな少女を連れてきた。そして3人並んで興味深そうにじっとこっちを見つめていた。
テントを張り終えると、こっちに来いと呼ばれ、今度は彼女たちのテントの中に連れていかれた。
「あがれ、あがれ」と彼女が言うので、靴を脱いであがらせてもらうことにする。中には暖炉があり、蒔がぱちぱちと音を立てて燃えていてとても暖かい。床にはトルコの絨毯が敷いてあり、奥のほうには蒲団らしきものが積み上げてあった。
とりあえず、床に座らされのんびりと出されたお茶、チャイを飲んでいると、妹と、お父さんが帰ってきた。二人は驚きながらも、この突然の異邦者を喜んで歓迎してくれた。姉と比べて活発な妹は、学校で先生をやっているらしく、いくらか英語を話せた。
「どこから来たの」
「日本だよ」
「日本!そんな遠くから。それでどこまで行くのよ」
「シンガポール」
「シンガー・・?」
彼らはシンガポールを知らないらしいのでぼくは嘘をついてしまった。
「うーんと、ほら隣のイランのことだよ」
「イラン!それは遠すぎるわ。いったいどこでバスに乗るの」
「いやバスは使わないんだ、自転車で行くんだ」
ぼくは少し得意気になって言った。
「自転車?」
不思議がる彼女に、先ほどの姉がトルコ語で説明した。そう言えば、トルコに入ってから自転車というものをほとんど見たことがないな。
「自転車ですって。そんなのは無理よ、どれだけ遠いか知っているの?いい、バスで行くのよ。アンカラからはきっとバスが出ているから」
「うーん、わかった、わかった、そうするよ」
この場はこう答えておいて方が良さそうだ。話の最中で、また違う夫婦が入ってきた。彼らは先程の少年の両親で隣のテントに住んでいるらしい。とりあえず握手を求められる。
「お腹はへってない?」
そういえば、今日は店さえ探せなかったので何も買えずに、夜は食事抜きだと覚悟していたところなのだ。なんて幸運。この場はありがたく食事をご馳走になることにした。
 お姉さんは外からガスコンロを持ってくると、鉄板の上で豆を焼きだした。豆がある程度焼けてくると、そこにトマトと香辛料を入れ煮立てる。そしてしばらくかき混ぜると、もう出来上がりだった。簡単な料理だ。床に大きな布を引いて、そのうえに料理を載せ、どうやらあぐらをかいたまま食べるらしい。インドのナンよりも平たいパンのようなものも出され、そのパンと豆を交互に口に運ぶ。
お姉さんは外からガスコンロを持ってくると、鉄板の上で豆を焼きだした。豆がある程度焼けてくると、そこにトマトと香辛料を入れ煮立てる。そしてしばらくかき混ぜると、もう出来上がりだった。簡単な料理だ。床に大きな布を引いて、そのうえに料理を載せ、どうやらあぐらをかいたまま食べるらしい。インドのナンよりも平たいパンのようなものも出され、そのパンと豆を交互に口に運ぶ。
今までで一番質素な食事だったけど、彼らの温かみのせいかとても美味しかった。
家事は女性がやるものらしく、男性は動こうともしなかった。食事も質素ながら、家のなかを見渡す限り無駄のない生活のように思えたが、決して貧乏ということではないらしかった。お父さんはウイスキーを飲んでいるし、しばらくして帰ってきたお兄さんは携帯電話を持ち、リーバイスのジーンズをはいていた。
夜になれば家族全員がこのおんぼろなテントに集って一緒に寝る。一人一人が家族をとても大事にしているということがわかる。
お酒を飲んでご機嫌な親父は、ぼくにまでウイスキーを進めてきた。ぼくがそれを一口飲むと、それを見ながら、満足そうに、そして本当にうれしそうに微笑んだ。ぼくに一番興味を持ってくれた二番目の妹は、「プレゼントよ」と言うと、トルコ語のミュージックテープをくれた。
彼らと知り合ったのはたった数時間前なのに、なんでここまで親切なんだろう。ぼくは日本では触れることができない、人間の温かみに触れた気がした。
|
