 |
|
 |
|
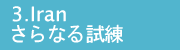 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
知らぬが仏の砂漠道 (パキスタン)
05
 22歳最初の日、ぼくは1日かけてムルターンの町を歩くことにした。まずは「世界の柱」という意味のシャー・ルクネ・アーラムと呼ばれる聖者廟を見に行き、その周辺のモスクを見学した。それから城壁に囲まれた旧市街を歩き、バザールで古着の長ズボンを購入すると、屋台でケバブをつまみ、食堂に入りカレーを食べた。フー・・
22歳最初の日、ぼくは1日かけてムルターンの町を歩くことにした。まずは「世界の柱」という意味のシャー・ルクネ・アーラムと呼ばれる聖者廟を見に行き、その周辺のモスクを見学した。それから城壁に囲まれた旧市街を歩き、バザールで古着の長ズボンを購入すると、屋台でケバブをつまみ、食堂に入りカレーを食べた。フー・・
お腹が一杯に膨れると、ぼくはやることがなくなってしまった。何をして良いのかわかなくなってしまったのだ。バザールを歩いても、モスクを見ても、ちっとも面白くなかった。ぼくは宿に帰ってボーッとした。旅が旅でなくなり始めているのかもしれなかった。旅は日常のことで、いつもそこにあるもので、その日常に驚きや感動をする事がなくなって来ているのかもしれなかった。
ただぼくに唯一刺激を与えてくれるのは自転車をこぐことなのかもしれない。自転車をこがないときは何をやっていいかわからないなんて、あまりにも長く自転車をこぎすぎちったかな。自転車をこがないとぼくは存在しない。我チャリをこぐ、故に我ありとでも言おうか。
夕食は高級中華料理屋に行き、一人でお祝いをした。高級と言っても1000円くらいだけど。そして翌日からはラホールを目指す。もうインドが近くにやってきているのだ。
イランに入ってから続いている、ぼくの人間嫌いはこの国にきて更に加速した。これも長期旅行者の悪い傾向に違いなかった。
もちろんパキスタン人もイラン人もいい人ばっかりで、フルーツを恵んでもらい、ご飯をおごってもらい、チャイに限っては何杯おごってもらったか数え切れないほどだ。ぼられる事もあったが、それよりもおごってもらうことの方が多いに違いなかった。みんな親切でやさしかった。ぼくはイランと違って、この国も、ここの人々も大好きだった。
それでも、ぼくは独りになりたかった。独りの時間を必要としていた。そしてここは独りになれない国だったのだ。
街を歩けば穴があくほどジロジロと見つめられる。食堂に入ると、誰もが振り向き、食べ終わるまでに5、6人が寄ってきて話し掛けてくる。走りつかれてチャイ屋に入り、チャイを飲んでゆっくりしようとすると。また人が来ては質問し始めるのだった。質問は毎度似通ったもので、まず「どこからきたの、から始まる」そして、次に「What is your name?」ここまではいたって普通の流れなのだが、次からはなぜか分からないが家族の名前を聞いてくる。「What is your father's name?」「What is your mother's name?」となり、それからも「What is your job?」「 What is your father's job? Mother's …」と簡単な単語を並び替えただけの意味のない質問が永遠と続くのだ。要するに彼らは知っている単語をすべて使いたいのだ。誰でもいいから英語で話してみたいのだ。この質問攻めには、もううんざりしてしまった。
もちろん、彼らの気さくな態度はありがたかった。本来ならそれは快く受け入れる好意だった。ぼくの旅行が短期間だったら、喜んで、いつでも誰でも相手にしただろう。そして現地人との交流を良いことも悪いことも、何でも喜んで受けただろうに。
しかし長期旅行を続けていたぼくの心は腐っていた。毎日何度も近寄ってきては話しかけてくる彼ら一人一人を、対応する心の広さなど、もうどこにも残っていなかったのだ。
しかも、ぼくは自転車で旅をしていたので、とりわけ沢山の人が寄ってきた。バスと違ってどんなに小さな村も通過するのだ、そして、旅行者が間違っても来そうにない村ほど、人々の反応は強かった。ただ、お茶を飲んで休みたいだけなのに、小さな村の小さなチャイ屋に寄り、お茶を飲み始めて5分もすると、ぼくの椅子の周りは大勢の人で埋め尽くされていた。試しに人数を数えてみると、大人から子供まで53人の人がいた。まるでその村の全員が集まってきているみたいだった。大勢に見つめられながら、自転車をこいで疲れた体を休めることはできなかった。
人が集ってくるチャイ屋で休むのが嫌になると、ぼくは道端に座って休み始めた。それでものんびりしようとすると、トラックが通る度に彼らは手を振ってクラクションを鳴らしてくる。自転車で通りかかった若者は、目の前で立ち止まると、不思議そうに何も言わずにぼくを見ていた。そしてその青年につられて、次に通った者も立ち止まる。こうして、5人、10人となっていくともう休めたもんじゃない。「ハイハイ、行きますよ、ここを去ればいいんでしょ」そう言ってぼくは再び走り出した。
そして村を通過するとき。
パキスタンの人口の多さのためか、どこにでも人はいたし、サッカル以降一時間も走れば、必ずといっていいほど、村の一つは通過した。ぼくが走っているただの一斜線のひびが入った道路、それでもアジアハイウェイと呼ばれるこの道路が、ほとんどの場合、そのまま村のメインストリートになっていた。そしてそのただでさえボコボコの道路は村に入ると未舗装のさらに悪化したひどい道路となった。その道路沿いに商店や食堂が並ぶ。それは100メートルであったり、3、400メートルのときもあった。
道沿いにバザールがあり、そこに押し寄せる大勢の人々がいる。馬車が荷物を載せのんびりと走り、何10頭もの牛やヤギが主人に引きつられうんこをしながら歩いている。トラックやバスがけたたましい音を上げながら通過し、その横をスクーターが煙を巻き上げながら走る。
そんな村を人を掻き分けながら通過する毎に、ぼくは発狂しそうになった。でこぼこ道を誰にもぶつからないように、神経を集中しながら走る。そこへ、トラックのクラクションが鳴らされる。通行人には呼ばれ、村人が勢いよく走って追いかけてくる。ぼくが反応しないと「シッ、シッ」と犬でも呼ぶように舌打ちを鳴らす。遠くからぼくに向かって、何人もの人が叫んでいる。
雨の後はこれにプラスして、牛や山羊のうんこ塗れの泥水の中を走らなければならなかった。
ぼくは、独りになりたかった。でもなれなかった。
テントはぼくの家だった。そこには自分一人の空間があるはずだった。でも、テントに泊まった時すらも完全なる独りを味わうことはできなかった。
どこにでも人の影はあったが、テントの設営場所には十分気を使って、できるだけ見つからないような場所を探した。なんせ一番怖いのは人間である。しかし、どれだけ注意深くテントを張っても朝になると、毎度のごとく発見された。
ある日、村や畑からも離れたさら地にテントを張った。朝には男がやってきて、何かくれと手を差し出してきた。道から外れた林の奥の、木と木の間に張った。朝には人の声がして、声数は増えそれでも無視して中にいると、テントの下から手が伸びてきてマッチをくれという。仕方なくテントから出ると、そこには5人の男がいて、たき火の準備をしていた。そしてぼくのマッチで火を点けると、たき火に当たりながらジーっとぼくを見つめていた。
どうやらこの国では、独りになるのも、隠れてテントを張るのも不可能なようであった。そしてぼくはノイローゼのように、独りになりたいと思い続けるようになっていった。
|
