 |
|
 |
|
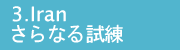 |
|
 |
|
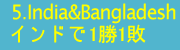 |
|
 |
|
|
|
インドで1勝1敗 (インドバングラ)
04
 「インドで一番インドらしい町」誰かがヴァラナシについてこう語っていた。
「インドで一番インドらしい町」誰かがヴァラナシについてこう語っていた。
バザールの狭い路地にぎっしりと並んだ商店、道路を埋め尽くすリキシャ、細い小道をうろつく牛、屋根から屋根へと渡り洗濯物にいたずらをする猿、マリファナを薦める宿の男、客引き、物売りの子供、そしてその騒がしい町の外れを流れる聖なる川、ガンガー。その聖地を訪れる大勢の巡礼者、物乞い、サドゥと呼ばれる修行僧、そして川縁で燃え上がる死体。
そのどれ一つをとっても、それは単体でインドという国を主張しているのだった。ここは騒がしい喧燥の町だった。しかしガンガーがもたらす、緩やかな流れのある町でもあった。
早起きをし、ガンガーの川縁に座り朝日が昇るのを待つ。川から立ち上がる霧が晴れると、川岸のチャイ屋でチャイを啜る。そしていつものようにゆっくりと街を歩き、食堂を見つけてはカレーを食べた。
今までインドでもっとも行ってみたかった街、ヒンドゥー教の聖地、そしてインドを凝縮した街。しかし、ここでも、ぼくの心は躍らなかった。ぼくには探求心が全くなくなっていた。言うなれば、入り組んだ路地裏を見てみようという気がなくなっていたのだ。一つ向こうの曲がりくねった道、その先に何が待っているのか、ぼくには行かなくても見えてしまう気がしたからだ。
燃え上がる死体を見ても、沐浴するインド人を見ても、それはただそこにあるものだった。物乞いも、物売りも、この喧燥さえも、すべては不動の物だった。
宿に戻るとお湯を沸かし、カップにインスタントコーヒーを溶かす。コーヒーを飲みながら屋上で本を読む。ぼくはそれだけで幸せだった。外に行かずとも、宿でのんびりするだけで満足してしまっていたのだった。
今は学生の旅行シーズンだった。街中や食堂で多くの学生を目にしたが、彼らの目はキラキラと輝き、全ての物に興味を示した。そして何よりも彼らはさわやかだった。
ぼくも旅の始めは、ああだったはずだ。そして堕落した長期旅行者を鼻で嘲笑った。しかし今のぼくはどうだ。果たして、今もさわやかであるか。町を歩かずに、宿で本ばかり読んでいるぼくは、あの学生達から見たら、トルコの安宿にいた「向こう側の人間」なのではないだろうか。
「長旅」その陰に潜む害虫が、ぼくの心を徐々に蝕んでるようだった。
この街には多くの長期旅行者がいた。3ヶ月、4ヶ月、そしてヴィザを取るために一度ネパールなどの国外に出ることを繰り返しては、永遠と住みついているような人。彼らの中には宿でガンジャと呼ばれる麻薬を吸いながら、一歩も外に出ない者もいた。彼らはもう旅人ではなかった。
ここまで落ちてはいけない。ぼくは旅人であり続けなければいけないのだ。そう思うと、ぼくはヴァラナシを後にした。
2日間走り、仏教発祥の地、仏陀が悟りを開いたといわれるブッダ・ガヤーに寄る。のどかな農村地帯の中にある本当に小さな村なのに、その村は人であふれかえっていた。
事情を聞くと数日前までダライ・ラマが来ていて、説法を説いていたという。そのためか、チベットや海外諸国から多くの人が集まってきていたのだ。無料に近い値段で宿泊させてくれるというスリランカ寺やミャンマー寺に行ってみたがどちらも満員だった。困った顔をしていると一人の若いアメリカ人女性が寄ってきて、寄付だけで泊らせてくれるという「international Meditation Center」と呼ばれる場所に案内してくれた。
寄付金で建てられたというその建物は、きれいな白い色の壁に囲まれたとてもきれいで立派な建物だった。でも、とても奇妙な場所であった。
受付に行くと、オレンジの僧着をまとった高齢の僧が出てきた。彼は何も言わずに薄い本をぼくに手渡すと、読めとしぐさした。パラパラとページをめくると、そこにはこの施設のガイドが書かれていた。面倒くさいので読んだよ、と返すと
「それで、どのコースを志望なんだ」
と彼は言った。コース?何か勉強会でもやっているのかな。
「いや、ぼくはただ泊めてほしいだけなんですけど」
そう言うと、彼はなんだと露骨にいやそうな顔をした。じゃあついてきなさいと言うと、宿泊棟らしき一番大きな建物へと案内された。建物の中は日も当たらずひっそりとしていた。
「シー」
しゃべってはいけない。彼はぼくに目配せをすると、二階へと上がっていった。
前から人が歩いてきた、だけどなんか変だ。その歩いてきた西洋人は、すり足でゆっくりと歩き、一点に自分の足元を見つめ、ぼくのことなど気づきもせずに通り過ぎていった。そして、足元を見つめたまま階段を降りていった。
案内された部屋に入ると、そこには蚊帳の付いたきれいなベッドが3つ並び、トイレとシャワーが併設されていた。寄与だけでこんなにきれいなところに泊っていいんだろうか、ここはぼくが今まで泊ってきたインドの、どの安宿よりもきれいだった。シーツをぼくに手渡すと、その高齢な僧は、しゃべっちゃだめだぞともう一度念を押し部屋を出ていった。
カチャッとすぐさまドアが開いたと思うと、今度はジーンズをはいた金髪の若い西洋人が入ってきた。どうやらルームメイトのようである。
「やあ、いま来たのかい?」
「そうだよ、たった今来たばかりだ」
一通りの自己紹介を済ませると、ぼくは唐突に聞いてみた。
「ここはいったい何なんだい」
「ああ、ここか、驚いたかい。ここはね・・」
再びドアが開き、今度は少し年配の西洋人の男性が入ってきた。
「シー」
話すな、とその金髪の青年は目で訴えていた。後から入ってきた男は、下を見つめたままゆっくりと歩き、トイレに入ると再び部屋を出ていった。ここがいったい何なのか、ぼくにはますます分からなくなった。
「彼は何?」
「彼は精神統一中なのさ。ここに泊っている者の多くは、金を払って精神的なコースをとっている。2週間のコースから、1ヵ月、それ以上に及ぶコースもある。その間は一言も話してはいけないんだ」
「誰とも?」
「そう、誰とも。だから君もここにいる間は彼らに話しかけてはいけないんだぜ」
「君はコースをとったの」
「いや、俺はここに泊っているだけだ。あれは結構高いんだぜ。それに誰とも話さないなんてできっこないさ。ばからしいよな」
「ほんと、あはは」
笑っていると再度ドアが開き、先ほどの精神統一中男が帰ってきたので、ぼくらはまた口をつぐまなければいけなくなった。
外に出てみよう。その重い雰囲気に絶えられなくなって、金髪の青年に手を振りぼくは廊下へ出た。通路では女性も含めた四人が下を見つめながら歩いていた。なんだか変な病院にでも紛れ込んでしまった気分だった。
すでに時刻は夕方だったので、日本寺へと行ってみることにした。そこにはまさしく日本のお寺があり、日本のお坊さんがいて、幼稚園らしき建物の庭には鉄棒が立てられていた。
懐かしかった。5時から難行をするというので、なつかしがてら参加してみることにした。もしかしたら大勢の日本人と会えるかもしれない、そんな期待もあった。
30分前になると、境内にはたくさんの外国人が集まってきたが日本人など一人もいなかった。彼らは仏壇の前に座禅すると、目をつぶって瞑想を始めた。5時になると日本人の僧が入ってきてお経を読み始めた。周りを見渡すと30人ほどの西洋人が目をつぶって真剣に聞いていた。彼らはみんなツーリストのようであった、それも長期旅行者に違いなかった。
 翌日、仏陀が悟りを得たという地に建つマハボーディ寺院へと行く。ダライ・ラマの滞在期に大勢の人が詰め掛けたせいか、辺りは祭りの後のように汚れていた。悟りを開いた場所の上に枝を張り巡らせる菩提樹の木は、思ったほど大きくはなかった。
翌日、仏陀が悟りを得たという地に建つマハボーディ寺院へと行く。ダライ・ラマの滞在期に大勢の人が詰め掛けたせいか、辺りは祭りの後のように汚れていた。悟りを開いた場所の上に枝を張り巡らせる菩提樹の木は、思ったほど大きくはなかった。
ここにも大勢の西洋人がいて、彼らは手のひらを3回合わせて地べたに這いずりながら祈る、チベット教特有の祈りを一心に行っていた。なんだか昨日の日本寺での座禅といい、このチベット流のお祈りといい、西洋人がやると不思議な感じがするんだなあ。
村をうろつき夕方になって宿に戻ると、昨日この場所を教えてくれたアメリカ人女性、ターニャが尋ねてきた。夕食を一緒にと誘われ、外に出て村の中心へと歩いた。
ターニャはもう、3年も旅行しているらしい。アメリカを出て3年、ヨーロッパそして、アジアへとゆっくり旅を続けてきたという。
「日本へも行ったのよ、コンニチワ」
彼女は微笑みながらそう言った。
「アメリカには帰る気はないのかい」
ぼくは聞いた。
「うん、戻ったとしても、もう住むことはないでしょうね。アメリカは嫌いなの。そりゃあ、家族は恋しくなるけど、私は異国にいることの方が好きだわ」
あのメディテーションコースは取ったのかと聞くと、彼女はうんと肯いた。
「ばかにするかもしれないけど、あれは結構いいのよ。私の友達も結構受講していたわ。なんていうか、長旅に疲れている人もいたし、そういう人にとっては、精神を落ち着けるにはとてもいいのよ」
「でも一言も話しちゃいけないんでしょ」
そう言うと彼女は笑いながら言った。
「そう、一言も!」
「ハハハハハ」
ぼくらは互いの顔を見合いながら笑った。
「これからどうするの」
そう聞くとターニャは胸を張って答えた。
「ずっと旅を続けると思う。旅が好きだから」
歩きながら話しているといつの間にかチベット人のテントが並ぶ地区に着いていた。案内されたのはその一角の小さなチベット料理屋だった。ドアを開けると、その小さい店内はすべて西洋人で埋められていた。
「よう、ターニャ」
「ハーイ、ターニャ」
あちこちから声がかかる。ほとんど全ての者が知り合い同志のようだった。そして、みんなこのブッダ・ガヤに長期滞在しているようだった。20人ほどの西洋人が一斉に箸を持ってトゥクパと呼ばれるチベット麺を食べている。面白い光景だった。
あのコースはどうだった、あれはいいと、みんながメディテーションコースの話をしていた。どうやらぼくが滞在しているメディテーションセンターに限らず、違う場所でもさまざまなメディテーションコースが行われているようだった。
きっとここは、ブッダ・ガヤは大きな精神病院なのだ。
心に何の迷いもないとき、元気なとき、自分に自信があるとき、そんなとき人はこんな「瞑想コース」など取るだろうか。取らないだろう。
誰もが、長期旅行者だった、そして誰もが精神的にいきづまっていたのだ。みんな心の中に迷いという爆弾を抱えていたのかもしれない。
そこまでして、人はなぜ旅を続けるのだろう。そもそも人はなぜ旅をするのだ。
そしてぼくは・・・
今はまだわからない。これは永遠の問いなのかもしれないな。
「私はずっと旅を続ける」
何の迷いもなくそう言い張ったターニャが、なんだかとても眩しく見えた。
|


