 |
|
 |
|
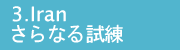 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
孤独と不安と葛藤と (ヨーロッパ)
11
 シーズンオフということもあってか、船には人が少なかった。一番安い外のデッキと、室内の席の差額がたったの3500円だったので、室内の椅子の上に寝ることにした。
シーズンオフということもあってか、船には人が少なかった。一番安い外のデッキと、室内の席の差額がたったの3500円だったので、室内の椅子の上に寝ることにした。
起きるともう朝になっていた。外に出てみると風がとても心地よい。疲れのせいもあってか、再び眠りにつき目覚めると船はもうギリシャ南部のパトラスに着いていた。
ここではようやくパスポートにスタンプが押され、船にも乗ったし、なんだか異国に来たなという気分になれた。
パトラスはゴチャゴチャと混み合った街だった。いやギリシャ自体がこんな感じなのかもしれない。イタリアとはまた違う、いや、そもそもヨーロッパと何かが違う気がする。銀行はきれいだったが、そのほかの商店はなんだか屋台のように汚く、スーパーも品揃えは良くなかった。
資材を積み上げて、埃をまき散らす工事中の道路がよけいに町を汚く見せた。通りを歩く人もイタリアやフランスの白人とはまた違った、少し浅黒い肌をしていた。ここは本当にヨーロッパだろうか、船に20時間も揺られるとこんなにも違ってしまうものなのだろうか。
両替を済ますと、そそくさと首都アテネへと走り出す。「アテネ」と書かれた標識に従うと、いつのまにか高速道路の入り口に来ていた。自転車はいいか、と聞くと、OKだといわれたのでそのきれいな幹線道路を走る。さすがに高速道路は路面が良い。100キロをオーバーする車との併走はあまり気持ちの良いものではないけれど、こちらも負けじとビュンビュン飛ばす。
右手には奥深い山と森が広がり、左手にはアドリア海が横たわっている。アドリア海の彼方には白線を描きながら商船が行き来していた。海の色は、イタリアやスペインとはまた違う、きれいな水色だった。どこかで見覚えのある色だな、そうだ、あの色だ。子供の頃、絵画実習の時に作ろうとした空の色、青と白の絵の具を混ぜた色にそっくりだった。
高速道路に飽きてきたので、降りて海岸沿いを走る。海縁に建っている家は、白くペンキで塗られていて、家と家の隙間からは波の形まではっきりとした、きれいな海が見える。ギリシャよ、おまえはなんてきれいで繊細なのだ。
翌日、昼飯を食べ、上陸記念にと昼からビールを飲み気分よく走っていると、道端に止まっていた車から突然呼びとめられた。
「日本人?」
サングラスを掛けたおばさんが日本語で聞いてきた。ぼくは不思議がりながらも、自転車を反転させ彼女のところに戻る。
そこには少し年増の東洋人らしい女性と、ギリシャ人のおじさんが立っていた。
「まあ、コーラでも飲みなさい」
強い日差しの中、ありがたくコーラを飲みながら彼女の話に聞き入った。彼女の名前は文子さん、日本人だ。歳は四十代中頃といったところだろうか。ギリシャ人と結婚してここギリシャに住んでいるという。これからのルートを話し、今日は野宿をすると言うと、それは危ないから家に泊まりなさいと誘われた。
「うちに来なさい、何泊でもしていいから」
ぼくはこのありがたい申し出に甘えることにした。いつのまにかずーずーしさが板に付いてきたなあ。彼らの家は、アテネの真南にあるピレウスという港町で、ここからの距離はかなりあった。しかし、今夜は日本食を食べさせてあげるという誘惑に乗り、彼らと別れると、ぼくは一目散に走り出した。
ピレウスに着いたころには、もうどっぷりと日は暮れていた。さっそく彼女の家に行くと、ベッドルームをひとつ貸してくれ、いつまでもいていいのよと温かい声をかけてくれた。彼女もぼくと同じく日本語で話すことを欲していたのかもしれない。
夕食は豪華な日本食だった。炊き立てのご飯に、味噌汁、梅干、ひじきに昆布と焼き魚。もーう最高、やっぱ自分の国の料理が一番うまいや。
少し気になるのはギリシャ人の旦那さんの態度で、元海兵隊員だったこともあり英語は話せるはずなのに、こちらから話し掛けてもあまり返事は返ってこなかった。ただ単に物静かな人なのか、それともぼくを歓迎してないのか少し不安になった。彼はいつまでも黙々とクロスワードパズルをやり続けた。
翌朝から、地下鉄に乗りアテネに行き、早速街をぶらつく。ヨーロッパとは思えないほど汚い街だった。地下鉄の駅は薄汚く、大通りに出ると排ガスがたちこめている。通りには屋台が出ていて、小さな金物屋が並び、市場に行ってみればなんともいえない臭いが漂っていた。
ヨーロッパの静かさは無いけれど、街には活気があった。だれもが皆元気だった。街の雰囲気もそうだが、人の顔にも街にも、アラブの血が混じり込んでいるようだった。
屋台で「スブラキ」と呼ばれる、串焼きをピタで包みそのうえに独自のソースをかけたサンドイッチを買い、それを口にくわえながら通りを歩く。何もかも新鮮だった。久々に真新しい土地に来た感じがして、心が震えた。
にもかかわらず、ぼくといったら、このアテネの最高の見所パルテノン神殿などを無視しては、ヴァージンメガストアを見つけCDを視聴し、本屋で立ち読みをし、ウィンドウショッピングをしながらプラプラと歩いているだけだった。都会に来るとどうしても日本でしていた生活がしたくなる。でも、都会の外にいるときは何もない田舎を自転車で走っているだけなんだから、これくらいがちょうどいいのだろう。
アテネ中心のオモニア広場のはずれを歩いていると、短パンにポロシャツという格好をした、いかにも旅行者っぽい外人が、地図を片手にキョロキョロしながら近寄ってきた。
「すみません、迷ってしまったんですが、ここはどこかわかりますか?」
歩き回っているだけあって地図は頭に入っている。まかしとけって
「えーと、ここはね・・」
と、教えている最中にもう一人、今度はサングラスをかけた怪しい男が近寄ってきた。男は胸元からさっと手帳らしきものを出しぼくらに見せると、すかさずそれをポケットに戻しこう言った。
「Police control. show me your passport(警察だ、パスポートを見せろ) 」
警官?それにしてもなんでいきなりパスポートを見せなければいけないのだ。そう言えばギリシャには偽警官が出没するって誰かに聞いたっけ。ジーパンに薄汚れたシャツ、一昔前の縁の大きいサングラス。こいつは見るからに偽者じゃないか。ぼくはそう確信し、ダイレクトに言った。
「おまえ偽者だろ」
男の何らかの反応を期待していたが、ぼくがそう言うと彼はあっさりときびすを返し、去っていった。何も言わずにだ。ぼくはおかしくって笑いが止まらなかった。そこで改めて、目の前にいる道を聞いてきた旅行者のことを思い出した。彼はそわそわして落ち着きがなかった。きっと何が起きたかわからなかったのだろう。
「あのね、彼は偽警官なんだよ。ああやってパスポートを見せた後、きっと今度は財布を見せろって言ってきて、それから・・」
「あ、もういいよ、じゃあね」
そう一言だけ言うと、その迷子旅行者は、ぼくの説明を聞く間もなく去って行ってしまった。何よりまだ道さえ教えてないのだ。なんなんだと彼の後姿を眺めていると、なんと先ほどの偽警官が曲がった道と同じ角を曲がるではないか。なるほどーこれは気づかなかった、そうか彼らはグルなのだ、二人で一組の詐欺師なのだ。
手口はこうだ、パスポートを出せと言われたときに、まずは旅行者を真似た相方が、偽警官にパスポートを差し出す。そして、それにつられて騙される側も不安がらずに出してしまうというわけだ。それにしても警官の役を入れ替えたほうがいい。彼はどう見ても警察には見えなかった。
 アテネに来て4日目に、やっとこパルテノン神殿を見に行く。日本を出発する時は一番楽しみにしていた場所の一つだったのに、いざ、その何十世紀も前に創られた遺跡を目の前にしてもぼくは特に何も感じることがなかった。自分に語り掛けてくる熱い感情がないのだ。ただ本で見たのと一緒だなと思っただけだった。でも、これを旅の冒頭で見ようものなら、心が震えるほど感動していただろう。
アテネに来て4日目に、やっとこパルテノン神殿を見に行く。日本を出発する時は一番楽しみにしていた場所の一つだったのに、いざ、その何十世紀も前に創られた遺跡を目の前にしてもぼくは特に何も感じることがなかった。自分に語り掛けてくる熱い感情がないのだ。ただ本で見たのと一緒だなと思っただけだった。でも、これを旅の冒頭で見ようものなら、心が震えるほど感動していただろう。
確かに旅をしつづけているうちに、物事に関する関心や感動が薄らいできているのを、うすうす感じてはい。毎日毎日刺激がなくなってきて旅自体が日常化していくのを。それにしたってパルテノン神殿を見て感動しないなんてかなりの重傷だ。ぼくには心のケアが必要です。でもこればっかりは日本に帰るしか治療法がないからなー。ハイ、結論、治療不可能です。長旅はするものじゃないのかもしれないなあ。
それでも、世の中美味い話には、大抵は裏があるのであーる(意味ありげ、乞うご期待)。
疲れは蓄積していた。それでもぼくは休むことなくこぎ続け、アテネに行ったらきりが良いから休もうとずっと思っていた。先は見えなくて、何度もあきらめかけ、投げ出したくなったけど、とりあえずアテネまで行けば何かが見えるんじゃないかと思い、こぎ続けてきた。だからこのアテネでは長く休もうと思っていた。エーゲ海には沢山の島々があるので、そこでのんびりするのがいいだろうと思い、ミコノス島へ行くことにした。
明日がその出発の日だった。いつもは黙って隣でパズルをやっているだけの、文子さんのだんなさんはなんだかやけに親しげだった。ぼくが行ってしまうのを少しは寂しがってくれているのだろうか、話しかけてきては手を擦ってきたりする。しかし、なんだかやけになれなれしい。文子さんが洗濯をしに行ってしまうと、もっと近寄ってきてマッサージと言いつつ、背中に手を入れてさすってきた。くすぐったいので声を立てて笑うと、
「シー!」
彼は文子さんの方に目配せしながらそう言った。そして今度はぼくのひざや足を擦りつつ「グッド」とか言っている。ぼくはぞくっとし、「またか……」と思った。おまけに今度のこいつは両刀使いだ。
彼女が寝てしまうと、今度は庭に出ようと首を降って合図をする。益々いやらしい。こんな遅くに庭にでて何をするというのだ。嫌だと断固拒否すると、
「I think you like」
だと。なにおー!人のことを馬鹿にしてるや。
「それは違う」ぼくは否定し、頭にきて自分の部屋に戻った。好きに見える?ホモに見えるのかな、少しショックである。このことは、とてもじゃないけど文子さんに言える話じゃないな。
これが美味しい話の裏話、であった。
|
