 |
|
 |
|
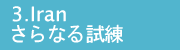 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
孤独と不安と葛藤と (ヨーロッパ)
10
 ローマに来てからすでに4日が過ぎていた。いつものように朝、宿を出ると街の雰囲気がどこかしら違う。道路は車であふれ、すれ違う人もなんだか足早だった。
ローマに来てからすでに4日が過ぎていた。いつものように朝、宿を出ると街の雰囲気がどこかしら違う。道路は車であふれ、すれ違う人もなんだか足早だった。
「もう9月1日かー」
一緒に歩いていた日本人がつぶやいた。そうか、こっちの休日も昨日で終わりなのか。今日から仕事始め、日本でも学校が始まっているんだなぁ。
旅を続けているうちに、時間の感覚なんて失いつつあった。それでも世界はいつもどおり動いているんだなと思うと、なんだか世間においていかれる気がする。いや、実際おいていかれているのだろう。
夜、ユースホステルの食堂で、首には数珠を巻き、汚い格好をした明らかに浮いている日本人を見つけた。何処から来たのかと尋ねると、彼はアジアを通ってここまで来たのだと答えた。
ついに見つけたのだ、ついに向こう側からの旅人に出会ったのだ。
今までも多くの日本人旅行者に会ったが、誰もがヨーロッパを旅しているだけで、その大半は学生だった。アジアの情報をのどから手が出るほど欲しかったぼくは、そのちょっと変ちくりんな彼を見つけ、心の奥からワクワクした。
「いやーヨーロッパは高いねー」なんてすかしている彼の周りには、話の聞きたさに大勢の学生旅行者が集まっていた。彼はいかにも得意そうである。
トルコの情報、イランの情報、パキスタン、インドの情報など、彼は多くの事を知っていた。例えば、イスタンブールの安宿や、イランのヴィザにいついてのこと、イランでの闇両替や、その方法。パキスタンの砂漠横断バスや、先は、現実味のないタイの情報まで教えてくれた。
あまりにも今まで出会ってきた旅人と違う容貌と態度に戸惑いもしたが、とりあえず、聞きたいことだけ根掘り葉掘り聞きだした。
夜、相部屋の電気は消され、仕方なく眠ることにするのだが、頭の先が火照っていてなかなか寝つくことができない。トルコ、イラン、パキスタン、インド、目の前の暗闇にはまだ見たことのないアジアの国々が広がっていた。そこには、ここにはない何かが待ち構えていそうだ。今の生活に少し飽きていたし、お金も急激に減っていたので早く物価の安いところに行かねばとも思っていた。
「アジア」
いい響きだね。少しずつではあるけど日本に近づいている気がする。この先の道にはいったい何がある。それを見つけに行こうじゃないか。
ローマはすばらしい街だった。それだけに名残惜しい気もしたが、主な観光ポイントは見てしまったし前に進むとしよう。ぼくは翌日には出発する決心をした。
出発の朝、ユースホステルで仲良くなった何人かの日本人の学生が玄関まで見送りに来てくれた。餞別に小説を五冊と、アルカリ電池を十本もくれた。どうしてみんなこんなに親切にしてくれるんだろう。今までどの場所でも、誰かしらに暖かく見送ってもらっている気がする。誰もが最後にこう言った「必ずシンガポールまでたどり着いてね」と。その期待を裏切らないようにしなきゃな。
 イタリアの南部から船でギリシャまで渡るため、南に下る。心はもうギリシャにあったので、ナポリにも寄らずに最短ルートを辿った。イタリアの中央には、アペニン山脈が横たわっていたので、毎日登りと下りの繰り返し。あたりは一面の畑で、電柱も立っていない緩やかな坂を長々と登り、途中に水場を見つけては上半身だけ水浴びをして、木陰で休んではまた走り出す。隣には線路が見え、農村をはしる道路ではごく希に車とすれ違う。高い木はほとんどなく、のっぺりとした丘が重なりながら地平線まで続いていた。
イタリアの南部から船でギリシャまで渡るため、南に下る。心はもうギリシャにあったので、ナポリにも寄らずに最短ルートを辿った。イタリアの中央には、アペニン山脈が横たわっていたので、毎日登りと下りの繰り返し。あたりは一面の畑で、電柱も立っていない緩やかな坂を長々と登り、途中に水場を見つけては上半身だけ水浴びをして、木陰で休んではまた走り出す。隣には線路が見え、農村をはしる道路ではごく希に車とすれ違う。高い木はほとんどなく、のっぺりとした丘が重なりながら地平線まで続いていた。
ある日、町につく10キロ手前で急に動けなくなった。体の全身から力が抜けていく。自分を動かしている力のもとが切れた気がした。いくら力を出そうとも前に進むことができなかった。これが、ハンガーノック現象というものだろうか。サイクリストや登山者がかかるという、カロリー不足で立ち上がれなくなる現象、いわば燃料切れ、体のガス欠である。でも本当ならば立ち上がれなくなるほどだというから、その一歩手前といったところだろうか。ぼくは、必死になってバッグの中の食料をあさった。あいにく行動食らしいものはなく、食料と呼べる物といったらパスタとトマトケチャップだけだった。仕方なくそれを食べることにした。生のパスタを口に入れ、ケチャップとミックスしながらガリガリ、ボリボリとゆっくり噛んだ。思ったよりいける!それを何度か繰り返すと、少しだけ力が沸いてきた。そこから40分ほど走って次の町に着くと、ぼくは一目散にスーパーへと駆け込み大量の食料を調達した。
スーパーの前で買った食料をひたすら食べていると、いつの間にか日が暮れてしまった。近くの畑の脇に寝袋だけ敷いて寝ていると、夜中に体格のいい3人の黒人の男がこちらへと歩いてきた。襲われるのかとドキドキしながら、薄目を開けて震えていると、彼らはこっちを睨みながらも、通り過ぎていった。安堵感が溢れると、そのままスヤスヤと眠りについた。
翌朝出発すると近くのガソリンスタンドに、昨日のような黒人が20名ほど屯って野宿をしていた。彼らは見るからにみすぼらしい格好をし、どこからか来た難民のようであった。昨日の連中もこの中の誰かだろう。何もなかったから良いものの、やはりヨーロッパといえど、野宿には細心の注意を払わなければいけないな。ぼくは自分の心にそう言い聞かせた。
ギリシャ行きの船が出ているというバーリの港町に着く間近の道端で一台の車に呼び止められた。中からは中年の小太りしたイタリア男が降りてきて、ぼくに話しかけてきた。
「何処に行くんだ?」
「バーリだよ、そこからギリシャに渡るんだ」
「そうか、オレはバーリのそばに住んでいるんだ。もし時間があるなら街を案内してあげるよ」
あまりにも突然の申し出だった。少し戸惑ったが、ぼくは一刻も早くギリシャに行きたかったので断った。
「時間があまりないんだ。休んでも一日、きっと街をちょっと見たら終わってしまうよ」
「そいつはもったいない。バーリのそばにはアルベロベッロっていう、白い家の町があるんだ。その町や、周りの観光地を車で案内してあげるのに」
なんだかあまりにも出来過ぎた話だった。しかしそれも魅力的だなと悩んでいると
「とりあえず、地図を見て考えなよ、説明するから車に乗りな」
と、彼はまた車に乗ってしまった。ひとまず車に乗ると、彼は地図を広げているのにかかわらず違う話をしてきた。
「イタリアの女性をどう思う?」
「うーん、とてもきれいだよ」
「もう、やることはやったのか」
「まさか、そんなことあるわけないじゃん」
「ふーん」
そう言いつつ、男はぼくの股間を撫でてきた。ぼくが先ほどかすかに思った予感は的中した。「こいつはホモなのだ」
いつもこうだ、海外に行くとぼくは決まってホモに声を掛けられる。極度のなで肩のせいだと日本の友人が冗談半分言っていたが、つまりは国境を越えてもてるってことだ。あーあこれくらい女の子が積極的によってきたら、いつでもいちころなんだけどな。残念ながらそんな目には一度もあったことがない。
「やめろよ」
そう言っても、彼は止めずに
「You like?」
だとさ。ぼくは半ば呆れ、そして頭にきて車を出た。するとそいつはエンジンをかけすぐに去っていった。なんなんだいったい。全くもって感じ悪いよ。ケッ、イタリアってプレイボーイの国だろ、だったらもっと紳士的になっていただきたいもんだね。
イタリア最後の目的地バーリに着くと、長時間のサイクリングのため、久々にケツから血が出ていて、ズボンに赤いシミができていた。痛いし、みっともないし、ホモには会うし今日は全然ついてねーぞ。くそー!
|
