 |
|
 |
|
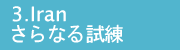 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
孤独と不安と葛藤と (ヨーロッパ)
07
 たっぷりと日本語での会話を堪能した後、ぼくはホステルを後にし、シャビーとアンナの家へと向かった。近くの電話ボックスで電話をすると少し日焼けしたシャビーが迎えに来てくれた。案内された二人が住むアパートは、古い建物の9階にあり、部屋が3つに広いテラスのある、すてきな場所だった。
たっぷりと日本語での会話を堪能した後、ぼくはホステルを後にし、シャビーとアンナの家へと向かった。近くの電話ボックスで電話をすると少し日焼けしたシャビーが迎えに来てくれた。案内された二人が住むアパートは、古い建物の9階にあり、部屋が3つに広いテラスのある、すてきな場所だった。
「タクジ、ここはあなたの家なのよ。リラックスしてくつろいでね」
出迎えてくれたアンナが言った。
シャビーは地元テレビ局の、夕方のニュースのキャスターで、アンナはジャーナリストで記事を書いているらしいが2人とも今は休暇中だ。マスコミの仕事だというのに強制的に一ヶ月も休みをくれるという。日本とは違うお国柄にびっくりだ。
シャビーは、背は小さいものの、トム・クルーズ似でとてもハンサムな顔立ちをしている。アンナは美人とは言えないまでも、かわいいくて性格の良いとてもすてきな女性で、とにかく二人は結婚はしてないものの、お似合いのカップルなのだ。
タリファからほとんど休まずにここまで自転車をこぎ続け、そのうえバルセロナに来てからというもの朝から晩まで歩き回っていたぼくの体には、明らかに疲れが蓄積していた。ぼくは何もせずに休みたかったのだが、親切にもシャビーとアンナはいろいろなプランを立ててくれているようだった。
翌日は朝から、シャビーのお姉さん、その旦那さん、そしてお母さんが来て一緒に郊外のモンセラート山に行く。山の中腹には修道院があり聖母マリアの信仰地として多くの巡礼者を集めていたようだがここもサグラダ・ファミリアと同じく今は観光地化されてしまっていた。
この帰りに森の中のレストランでスペイン料理をご馳走になる。ソーセージの山盛りに、トマトを塗ったパンにハム、豆にグラタン、最後はクリームのデザートにコーヒーと、ぼくは気持ちが悪くなるほど満腹になってしまった。
シャビーは何かあるたびに「ティピカル(典型的な)」と言った。そしてそれはぼくらの合い言葉となった。
「タクジ、これがティピカルスペイン料理だよ、食べなよ」
「タクジ、これがスペインでのティピカルなパンの食べ方だよ、オリーブオイルを塗ってなあ」
「タクジ、これこそティピカルなスペインのデザートだ」
「タクジ、スペインのティピカルな習慣はな…」
「オーケー、シャビー。ティピカルな日本食っていうのは寿司って言うんだぜ」
「それからティピカルな日本人っていうのは、やたらと写真を撮ってね…」
と永遠と議論が続いた。
満腹のせいもあって、帰りの車ではぐっすりと眠ってしまった。家に着いて起きて車を出るとみんながにこにこ喜びながら寄ってきた。
「あなたはシエスタをしたわ」
「スペイン人が何でシエスタをするかわかったでしょう」
「タクジ、おまえはティピカルなスペイン人と同じ行為をしたんだ」
シャビーが付け足した。
本当は明日にはここを発つつもりだった。でも、もっと泊まっていけよという彼らの厚意に甘えて滞在を一日伸ばすことにした。明日はのんびりしようと思うと、じゃあ明日の昼はお母さんの家でパエリアだと言われ、夜はシャビーの姉さん、ナタリーがご馳走してあげると言いはり、明日も忙しくなりそうだった。
モンセラートから帰ってきてからは彼ら家族はテラスで雑談に花を咲かせていた。スペインは物価が安く、経済力も決して強いとは言えない国だったが、経済大国と言われる日本と比べて、この国の人の心のなんて豊かなことだろう。
今日の朝食は十時、昼食は三時、そして夕食は十一時半。休暇中とはいえ、スペイン人の食生活って一体・・・
 朝、自転車を整備する。前々から前輪の調子がおかしかったので、大事を取って自転車屋に持っていってみることにした。どうやら、ハブの部分に異常が見られるようだった。
朝、自転車を整備する。前々から前輪の調子がおかしかったので、大事を取って自転車屋に持っていってみることにした。どうやら、ハブの部分に異常が見られるようだった。
「彼はこれから自転車でシンガポールまで行くんだ」
付き添い兼通訳のシャビーがなんだか誇らしげに言った。
「この自転車でかい?」
自転車屋の若いあんちゃんは信じられないような顔をした。その話が本当だとわかると、今度は 自転車そのものに対して不満があるようだった。
「この自転車は、そんな長距離には適さない。第一パーツが良くない。それほどの事をするなら、それなりの部品が必要だ」
確かにこれは安い自転車だった。でも定価はけっこうな代物だったんだけどなあ。それにしてもまだ8分の1しか来てないのにもう故障なんて、いったい最後までたどり着けるのかと急に不安になる。とりあえず修理に丸一日かかると言うので出発をさらに延ばさざるを得なくなってしまった。でも明日はシャビーの休暇最後の日だ。その日くらいアンナと二人でいたいだろうと思い遠慮すると、シャビーはぼくの肩を叩きながらこう言った。
「いいんだタクジ、頼むから泊まっていってくれ。最後の休日をおれの日本人の友達と過ごすなんて最高じゃないか」
ぼくはシャビーの厚意に甘えきってしまうことにした。本当に彼はなんていい奴なんだ。
 昼にシャビーの実家に行くと、なぜか兄弟が勢ぞろいしていた。家庭的な味のパエリアを食べ、ドクタースランプの話しやドラゴンボールについて盛り上がる。そして夜はナタリーの家で、軽く生ハムやビールをご馳走になった。
昼にシャビーの実家に行くと、なぜか兄弟が勢ぞろいしていた。家庭的な味のパエリアを食べ、ドクタースランプの話しやドラゴンボールについて盛り上がる。そして夜はナタリーの家で、軽く生ハムやビールをご馳走になった。
本当になんて人たちなのだ。このまったくの赤の他人であるこのぼくに、なぜここまでのほどこしをしてくれるのだろう。こんないい人達、世界中を捜したっているもんか。翌日は念願かなって手紙を書いたり日記をまとめたり、やっとのんびりと過ごす。夕方になるとシャビーとアンナの二人がティビダボと呼ばれる、バルセロナ市外を一望できる山の頂上につれて行ってくれた。碁盤の目のように分けられたバルセロナの街をはるか彼方から眺めるというのは、確かにすてきなことだった。しかし、そのきれいな風景よりも夕日に照らされたシャビーとアンナのほうが美しかった。つくづくお似合いのカップルだなあ。
「I will really miss you」
ぼくは心からそう思った。
「私たちもよ。明日から寂しくなるわ。もしこの旅の途中で寂しくなったら、コレクトコールで電話してきなさい。いつでも話し相手になるから」
彼らは間違いなく、ぼくが今まで出会った中で最高の、世界一のカップルだった。
出会えて本当に良かった。
結局バルセロナに7泊。いつまでもいたかったが、そろそろ行かねばならない。本当にすばらしい街だった。
シャビーが最後に言った。
「Takuji ,This is Your Home.」
だからいつでも来いと。ぼくらは日本で、そしてまたいつの日かバルセロナでの再開を誓い合った。
別れはいつも辛いものだが、一人になると、それはそれで何からも解き放たれたように自由な開放感を感じた。ペダルに力を入れてガンガン飛ばす、極めて快調だ。やっぱり心も体も十分に休めたのかな。さあ、先に進まねば、次に目指すはローマだ。
バルセロナを出たのは12時だったが、がんばって夜の8時までこぎ150キロ進み、フィゲラスに着く。急いでユースホステルに行きテレビを点けた。今日からシャビーは仕事始めだと言うので彼の番組を見る約束をしていたのだ。テレビをつけるとすぐにニュースが始まりスーツ姿のシャビーが出てきた。ぼくはあまりの嬉しさに
「これはぼくの友達なんだよ」
と叫んだが、いまいちみんな信じてないようだった。今日は偶然にも日本のサッカー選手の川口を取り上げていた。いいゴールキーパーだと言っているようだった。
テレビのことを伝えるために電話をかけた。
「もしもし」
アンナのやさしい声がぼくの心を打つ。今日別れたばかりだというのに、すっかり彼らを恋しくなってしまった。
「テレビをちゃんと見たよ、それを言おうと思って」
「ありがとう。今日は日本のニュースを取り上げたので、おまえのことを思い出したよ。今ちょうど拓史のことを話していたんだ」
またいつか絶対に会おうと、ぼくらは再び誓い合った。
|


